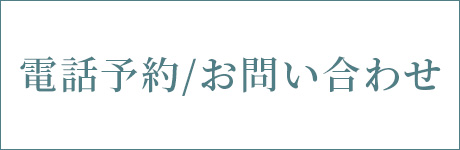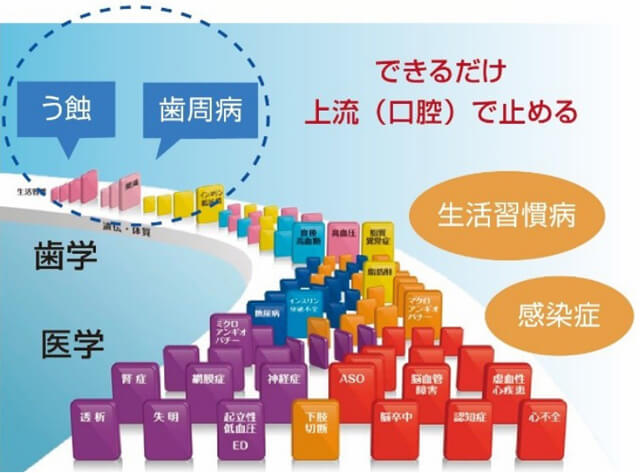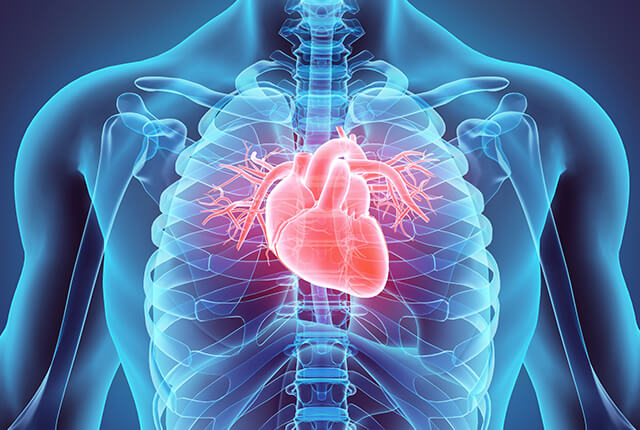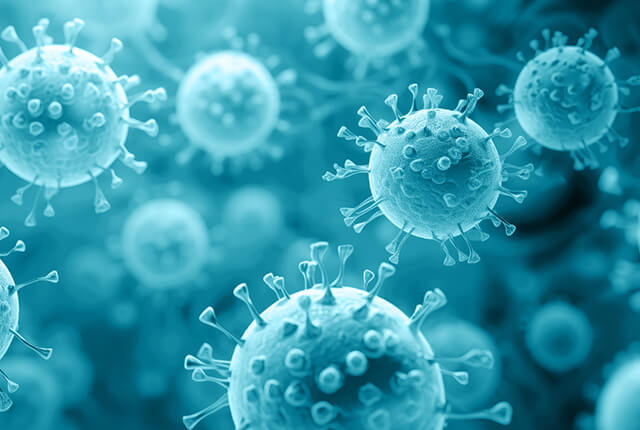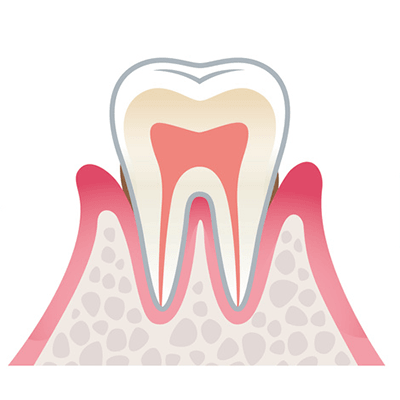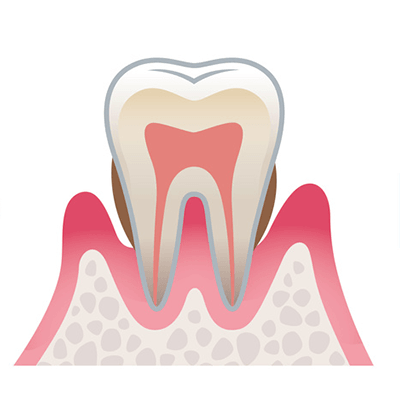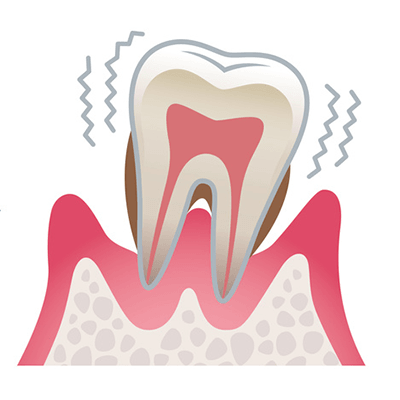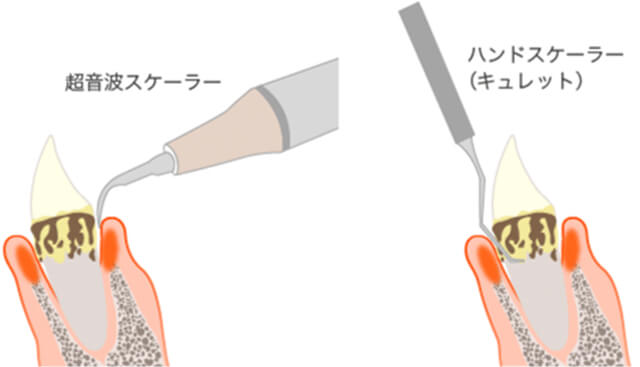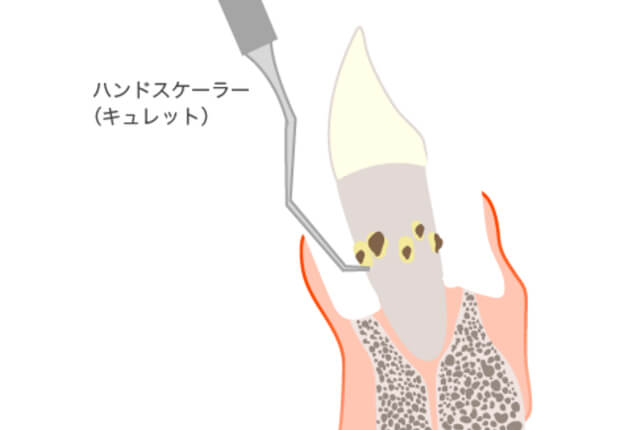当院を気持ちよく
ご利用いただくために
キャンセルポリシー
1. キャンセル通知期限
ご予約のキャンセルや変更は、できるだけ早めにご連絡いただけると幸いです。24時間前までのご連絡をお願いしておりますが、急な事情がある場合は遠慮なくご相談ください。
2. 予約の変更
予約の変更も24時間前までにご連絡いただけると助かります。柔軟に対応させていただきますので、どうぞお気軽にお知らせください。
3. 無断キャンセル
ご都合が悪くなった場合は、必ずご連絡をお願いいたします。無断キャンセルが続く場合、次回のご予約が取りづらくなることがあります。